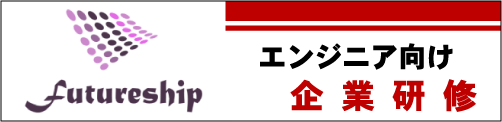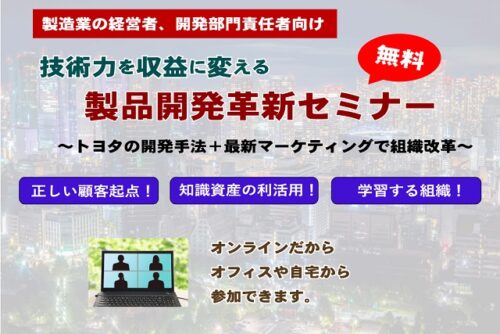質問力を高めるとロジカルシンキング力が上がって仕事が出来る人になる
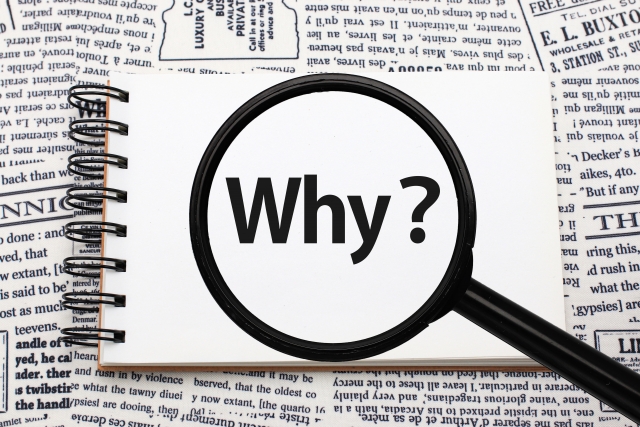

良い質問をする人って仕事が出来るように見えるけど何故かな?
会社の会議で良い質問をする人、国会で鋭い質問をする議員の人って、出来る人に見えますよね?質問力を高めて仕事が出来る人になりたいけど、どうな風に自分を磨いていけばいいか知りたい。
仕事が出来るとはモノゴトの本質をしっかりと捉える力です。モノゴトの本質を捉えることが出来る人は、会議や人とのコミュニケーションの中で、議論を活性化させたり、議論を正しい方向に誘導する良い質問が出来る人です。
技術組織で問題解決の思考プロセスを指導してきた経験から、ロジカルシンキングで質問を力を高めて、仕事が出来る人に変わる方法について説明していきます。
本記事の内容
- コミュニケーションにおける質問の役割
- 質問を生み出す思考プロセス
- ロジカルな思考で質問力を高める
- 仕事力を上げる質問テクニック
- まとめ
コミュニケーションにおける質問の役割

質問というのは、会議とか会話、コミュニケーションの中でわからないことがあったときに、相手に聞くということが基本です。
しかしながら、多くの人が経験していると思いますが、会議やセミナーでの質問内容で、その人が実はどれだけ理解しているのか、ということがわかってしまうだけでなく、質問者の知識力、性格やコミュニケーション能力、つまりその人が出来る人かどうかがかなりわかってしまうように思います。
言い換えると、質問にはその人の能力が表れる、つまり質問力は能力そのものなのかもしれません。
(参考記事:「質問力は武器になる」)
国会での論戦で野党議員が鋭い質問をすれば、この人は出来るなと思うし、そしてその鋭い質問で政府は失策などについて追い詰められていきます。
鋭い質問は、問題の本質を暴き出して、議論を正しい方向に導くわけです。
企業の中でも、会議でたくさん質問をして会議の方向性をコントロールするような人がだいたい出世してますよね。
口だけの人と陰口を叩かれる場合もありますが、ある意味、社内のコミュニケーションである程度の役割を果たしていそうです。
今は警察の人と話ことはほとんどありませんが、高校生のころバイクに乗っていると良く警察の人に呼び止められて話を聞かれることがありました。(悪いことしてたわけではありませんよ。)
色々と質問してくるんですが、しばらく話していると同じような質問を繰り返してきます。さっき言ったじゃないかと思ってイライラした記憶がありますが、実はあれは言っていることに矛盾がないか、嘘を見抜くための会話術なんですよね。
テレビの刑事ドラマでは、出世しない変わり者の刑事が、他の人とまったく違う視点で疑問を持ち続けて、犯人に鋭い質問をしたりして、結果、その人が事件を解決するなんて良くありますよね。
こうやって見てくると、質問というのは、コミュニケーションの中でとても重要な役割を持っているようです。
質問は、単にわからないことを聞くということだけではなく、質問をすることで論点の矛盾を浮き彫りにすることがあります。
聞いているというよりは、明らかに矛盾を追及するために質問をするわけです。
嫌味なことをしているのではなく、発表者も他の聴取者も気づいていないことを気づかせることによって、参加者全員に正しい認識をリマインドさせるということになります。
質問は、議論やコミュニケーションを活性化して、正しい方向に導く潤滑剤のような役割を果たしているのかもしれません。
質問を生み出す思考プロセス
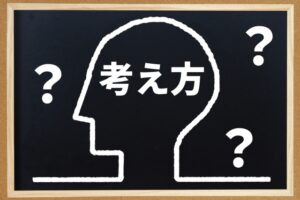
質問はどこから出てくるのでしょうか?
基本的には、発言の内容が自分が聞きたかったことと違う、自分の理解していたことと違うということとか、もう少し深く聞きたいなどの想いで質問に至る場合、つまり聞き手として本当に聞きたいことが頭に浮かんでくるということが一番目の質問の出どころということです。
ここで先ほど説明した質問の役割を思い出してみてください。
議論やコミュニケーションを活性化、そして議論を正しい方向に導く役割を考えると、聞きたいこと以外にその役割に則した質問が必要になってくることがわかります。
この役割を果たすためには、聞き手は説明者の話のパーツが、どのように繋がっていき、どんなストーリーになるのかを考えながら聞く必要があります。
こういうと、聞き手がそういう役割を意識してやっているように聞こえるかもしれませんが、実は、真剣に人の話を聞くというのはそういうことなのだと思います。
話のパーツの繋がりに違和感はないか、この先、話はどうなっていくのか、話し手の意図はどこにあるのか、ということを真剣に話を聞こうとする模範的な聞き手であれば、無意識にそんなことを考えながら人の話を聞いているのです。
議論を活性化する、あるいは議論を正しい方向に導くことができる優秀な聞き手は、無意識に、相手の話のストーリーを頭の中で追いかけて、論理的な矛盾点を見つけたり、別の角度からの見方をしたり、本来目指すべき議論の方向と話し手のストーリーのズレを捉えたりすることが出来るのです。
ストーリーで考えるということは、相手の話を自分事として聞くということです。
良い質問で会社の中での議論やコミュニケーションに貢献するためには、基本的には相手の話を自分事として聞くことから始めるといいと思います。
その上で、相手の話をストーリーとして聞くこと、ストーリーを考えながら話のパーツの論理的なつながりを追いかけることが出来るようになると、コミュニケーションを活性化する良い聞き手になれます。
ロジカルな思考で質問力を高める

話し手の言いたいことを自分事として真剣に聞く姿勢が出来たら、次に目指すのは質問力を上げて仕事が出来る人になることです。
質問力を上げるのは、ずばりロジカルシンキングです。
ロジカル(論理的)にモノゴトを考えるということなのですが、ロジカルシンキングについては別記事で詳細に説明しているので、参照ください。
ロジカルシンキングをごく簡単にまとめると、
- ものごとを因果関係で捉える
- なぜそうなるかを深堀する
の2点だと思っています。
相手の話を聞いてストーリーを頭に描いたときに、ひとつの事柄から次の事柄へ「XXすればYYする」というロジックに不自然がないかを感じ取る力がロジカル力です。
また、5歳児のように「なぜ」と疑問を持ち続ける力、疑問に対して思考し続けることもロジカル力です。
多くの人、つまりロジカル力の弱い人は、「誰も気にしてないから」「それはそういうものだから」といって疑問を持つことを放棄しているのだと私は思っています。
「なぜなぜ5回」と言われますが、実はとても大事なことで、かつなかなか実行できないことです。
質問力はロジカルシンキングと直結しています。
「なぜなぜ」という癖を持つことと、相手の話をストーリーで捉えて因果関係で重要な疑問点を思い浮かべる力を養っていきましょう。
仕事力を上げる質問テクニック

別記事「ロジカルシンキングを鍛えて上司を見返そう」にも記載していますが、ロジカル力を上げて質問力を高める2つの魔法の言葉があります。
- それはなぜですか?
- それをするとどうなりますか?
この2つの言葉を自分の口癖にしてください。
あるいは人の話を聞きながら、頭の中でこの2つの言葉を繰り返すようにしてください。
「それはなぜですか?」は、やりすぎると人によっては煙たがられるかもしれません。
お子さんたちに質問攻めにあって苦労したことがある人はわかると思いますが、めんどくさいというのが最初にくるのかもしれませんが、実は自分がわからないことを放置していることに気づかされて自分にもイライラしているのかもしれません。
しかしながら、職場でのコミュニケーションで誰かが「それはなぜですか?」を連発するようになると、メンバーの考え方が少しずつ変わってきます。
思い込みやわかったふりを止めようという雰囲気が出てきます。
試してみてください。
「それをするとどうなりますか?」というのは、因果関係ロジックを確かめるために使います。
「お客さんとの関係性が悪い」と「お客さんのことが理解できない」、「お客さんを理解できない」と「お客さんの望む製品がわからない」、「お客さんの望む製品がわからない」と「ヒット商品が生まれない」、「ヒット商品が生まれない」と「売り上げが上がらない」という因果関係があるとします。
確かに因果関係は正しそうですが、例えば、ヒット商品が生まれなくても、既存商品のニーズが安定していれば売り上げは上げられますよね。
因果関係はストーリーでもあります。
それぞれの関係をしっかり掴むことが第一歩で、次にそれぞれの因果関係に矛盾や思い込みがないかを考えることです。
上の例では、必ずしもヒット商品だけが売り上げを上げているのではないということを見つけた例です。
また、因果関係を逆にたどっていくのが、「なぜなぜ」思考でもあります。
売上が上がらない、という悩みに対して、「ぞれはなぜか?」を考えていきます。
ヒット商品も出ないし、既存商品の需要も減少している。だから売り上げが落ちている、ということを突き止めます。
次に、「なぜヒット商品が生まれないか?」ということを考えます。お客さんのニーズがわかっていない、というのも一つの原因と考えて、どうやって顧客ニーズを正確に掴むかを考えていきます。
さらに「なぜお客さんのニーズが掴めないのか?」と考えて、お客さんとの関係性に問題がないかと考えを深掘りしていくのです。
このように因果関係となぜなぜの両方を考えることで、モノゴトの本質を掴むような思考法を身につけると、建設的な質問が次から次へとわいてきて、周りからは仕事が出来る人だと見られるようになります。
まとめ
いかがですか?
質問力の威力を理解いただけましたか?
また、その質問力はロジカルシンキングを鍛えることで高めることが出来ることを理解いただけたでしょうか?
ロジカルシンキングは元々のセンスというか、資質に依存している部分は大きいのですが、実は誰でも鍛えることができると、これまでの経験から考えています。
弊社には、ロジカルシンキングを鍛える育成ツールがあります。
TOC(制約の理論)の思考プロセスを活用したツールをぜひお試しください。
ロジカルシンキングのトレーニング方法を半日のセミナーで解説しています。
セミナータイトル: 論理思考力強化セミナー(オンライン)
概要:
1.論理思考力(ロジカルシンキング)概論
2.TOC(制約の理論)の概要
3.問題を客観的に捉えるクラウド(対立解消図)
4.問題の連鎖(因果関係)の理解
講師: 賀門宏一(フューチャーシップ代表)
投稿者プロフィール
- 製品開発革新のプロパートナー
- フューチャーシップ(株) 代表取締役
技術者のキャリアアップ請負人。日米複数の製造業で製品開発現場30年以上の経験、エンジニア育成の経験をもとに、エンジニアの活性化を通して日本企業の再生を目指し奔走中。
最新の投稿
 コラム2023.01.17製品開発プロジェクト・マネージャーを育成する実践型PM研修
コラム2023.01.17製品開発プロジェクト・マネージャーを育成する実践型PM研修 コラム2023.01.06組織を変える提案、課題解決の提案力を育成する社内研修
コラム2023.01.06組織を変える提案、課題解決の提案力を育成する社内研修 お知らせ2022.09.29研修コース例 ~技術戦略書の作成研修
お知らせ2022.09.29研修コース例 ~技術戦略書の作成研修 お知らせ2022.09.29研修コース例 ~製品開発革新の実践研修
お知らせ2022.09.29研修コース例 ~製品開発革新の実践研修
フューチャーシップ(株) 代表取締役
技術者のキャリアアップ請負人。日米複数の製造業で製品開発現場30年以上の経験、エンジニア育成の経験をもとに、エンジニアの活性化を通して日本企業の再生を目指し奔走中。